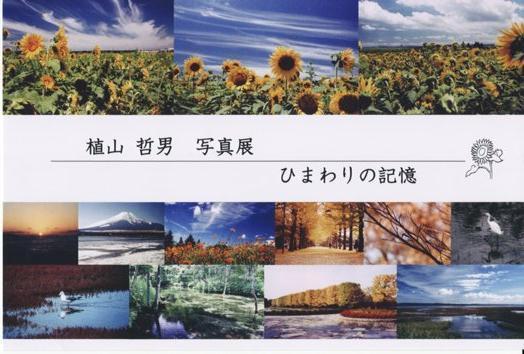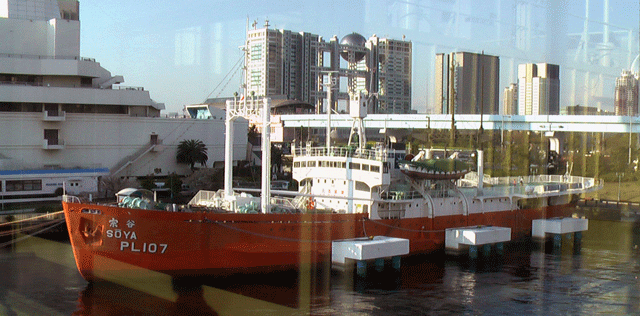夜会Vol.17『2/2』開幕の3日前、11/16にリリースされたニューアルバム『荒野より』 。
つねに新たな境地に挑戦しつづける「前のめりのラディカリズム」――それは、アルバムに限らず、夜会やコンサートツアーも含めて、中島みゆきの新作に触れるたびに感じてきたことではあるが――を、改めて強烈に印象づけられるアルバム、というのが第一印象だった。
その意味では、私にとっては、かつて彼女の初期 (1970年代後半) の作品に初めて触れた頃に受けた衝撃を――もちろん、内容的な印象はまったく異なるが――思い出させられる作品でもある。
夜会が中島みゆきのライフワークとして、事実上彼女の活動の中心となって以来、アルバムやツアーは、どちらかといえば周縁的な (やや軽めの) 位置づけになったかに思われた一時期もあった。
しかし、ここ数作のアルバム――とくに「I Love You, 答えてくれ」「DRAMA!」「真夜中の動物園」の3枚――や、2010~11年のツアーでは、彼女が夜会に注いできたエネルギーが、もはや夜会という枠組みにさえ収まりきれず、アルバムやツアーにまで溢れ出してきたかのような印象をしばしば受けた。
この新作では、そのエネルギーの波が今まで以上に強く高く、私の耳に、心に向かって押し寄せてくる。
個々の曲についてきちんと感想を書くのは、もう少し聴きこんでからにしたいが、夜会との関係を中心に、とりあえず心にかかったいくつかのことについて、書き留めておきたい。
これまでは別冊になっていた歌詞の英訳が、今回はリーフレットの歌詞の右ページに印刷されている。タイトル曲「荒野より」の「荒野」は、Wilderness ではなく Icy reaches と訳されている――直訳すれば、「氷におおわれた地帯」ということか。
この曲が主題歌として使われているTVドラマの舞台である「南極大陸」を直ちに想起させる訳語ではあるが、最近のラジオ (福山雅治のANNなど) で、この曲の原型は14,5年前にできていた、と彼女自身が語っていたこととの関係が気にならないでもない。
もちろん、英訳は最近作られたものなのかもしれないが、ただ、10年少し前といえば、ちょうど夜会『ウィンター・ガーデン』が構想されていたであろう時期にあたる。
物語のシチュエーションはまったく異なるし、「荒野より」の曲調も、あの夜会の舞台にはあまりそぐわないのは事実だが、『ウィンター・ガーデン』もやはり、氷原の中で孤独に誰かの帰りをまちつづける〈犬〉を主人公とした物語だったということ――これはなんだか、偶然の一致とは思えないような気もするのだ。
「荒野」という言葉は、終曲「走」にも――1曲目とループをなすように――登場する (ここでの「荒野」の訳語には、より一般的な Wilderness が当てられている) 。
迎える声は風の中 ゴールは吹雪の中
どこまでもどこまでも荒野は続いている
前の記事でも触れたとおり、ここでも「荒野」は、目指すべき遥かな場所に辿り着くまでに越えてゆかねばならない、現実の世界の風景としてある。その「荒野」が果てしなく続くがゆえに、その中を駆け抜けてゆく「走」もまた、果てしがないのだ。
「帰郷群」は――「彼と私と、もう1人」「旅人よ我に帰れ」とともに――間もなくスタートする夜会Vol.17『2/2』で歌われる (であろうと思われる) 曲である。
「ひと粒の心」という、まさにひと粒の短い言葉を、何度も――音程を微妙に変えながら――繰り返してゆく、実験的とも言うべき曲構成。こういうところに、私はとりわけ、中島みゆきのラディカリズムを強く感じる。
ひと粒の心 ひと粒の心 ひと粒の心 ひと粒の心
ひと粒の心 ころがりだす
この冒頭を初めて耳にしたとき、私は反射的に、夜会『今晩屋』の第一幕で、縁切寺の中から転がりだしてくる、あの無数の紙風船を思い浮かべた。あの紙風船たちも、おそらくは、封印された過去の縁、過去の記憶という「故郷」へと帰ろうとする「群」だったのだと思う。
そのことは――やはり前の記事でも想像した通り――『24時着0時発』での、廃墟堰によって故郷への道を遮られていた〈鮭〉たちの場合も同様だった。
運んでゆく縁 (えにし) 運ばれてゆく縁
身の内の羅針盤が道を指す
産卵のため、生まれ故郷の河へと過たず遡上してゆく鮭たちの姿をも、この短くも力強いフレーズは、彷彿とさせずにはおかないではないか――。
「帰郷群」の後半では、夜会Vol.7『2/2』の曲「誰かが私を憎んでいる」が、さりげなく引用される。この手法は、 「旅人よ我に帰れ」ではより大々的に、やはりVol.7のオリジナル曲だった「幸せになりなさい」の――ほとんど唐突な印象さえ与える――長い引用というかたちで用いられている。
歌詞カードを見ると、この引用部分は、
(植えつけられた怖れに縛りつけられないで)
(ただまっすぐに光のほうへ行きなさい)
……
と、括弧でくくられて表記されているのが興味深い。
唐突な連想かもしれないが、宮沢賢治の詩にしばしば登場するこうした括弧つきの詩節について、天沢退二郎が、「もうひとりの賢治の声をそこに重ね合わせるポリフォニー」 (記憶に頼って書いているので正確な引用ではないが) というふうに呼んでいたのを思い出す。
この曲に括弧つきで引用される「幸せになりなさい」も――夜会Vol.7のストーリーから類推する限り――まさにそうした意味で、「我に帰れ」と呼びかける恋人・圭の声と、莉花のもうひとりの自分――より正確には、姉・茉莉が異界から呼びかける声――とのポリフォニーというべきものなのだろう。
なお、こうした引用手法が初めて用いられたのは、おそらく夜会Vol.12『ウィンター・ガーデン』 (再演) の1曲目、「騙りの庭」でのことだ。
ずっとずっと信じて待ってる
誰を誰を待つのかだけ忘れてるのは 何の罰なのだろう
思い出すなら 幸せな記憶だけを
楽しかった記憶だけを
固く約束した人を
太字は、Vol.12では終曲となる「記憶」の一節である。
上記の〈犬〉 (中島みゆき) が歌うこの一節こそは、その前生の記憶が再生されるエンディングへの伏線であり、その意味で、それはやはり異界からの声とのポリフォニーだった。
アルバムの最後を飾る上記の3曲を通じて言えることだが、中島みゆきのヴォーカルの、おそらくは最もベーシックなスタイルともいうべき、地声に近いストレートなアルトが、とても魅力的だ。
とりわけ、「旅人よ我に帰れ」の、
真実の灯をかざして 帰り道を照らそう
の最後の「う」の確信に満ちた力強い低音は、「帰る」べき場所へと心を誘う、限りない懐かしさに満ちた声として、私の胸の底に響いた。
――他の曲についても書くべきことは多いが、夜会初日の前日という、慌しく気もそぞろな時でもあるので、とりあえずはここまでにしておき、残りは他日に譲りたい。