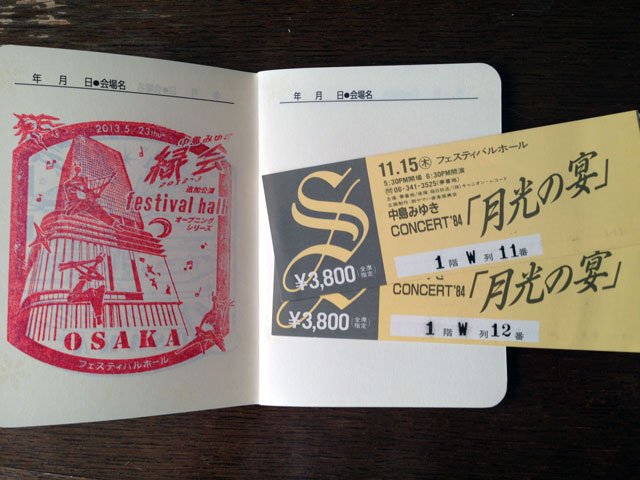9月14日(土)の夕方、新国立劇場・中劇場でのミュージカル「SEMPO」を観てきた。
2008年春に同じ劇場で公演された作品の再演である。この初演を私はライヴでは観ていない。
もちろん、中島みゆきが6つのオリジナル曲を提供したことが気になってはいたのだが、ミュージカルというジャンルへのなじみの薄さと、中島みゆき自身が出演するわけではない舞台を東京まで観に出かけることへのためらいがやはりあった。
だが、彼女の2009年のアルバム『DRAMA!』に (夜会「今晩屋」からの7曲とともに) 収録された「SEMPO」の6曲には、初めて聴いた時からとても強く魅きつけられた。
――あれらの歌が、いったいどんな場面で、どんな物語の文脈の中で歌われたのか。
私の中で火がついたこの問いは、初演のDVDを通販で購入して観ることで、ある程度は解消された (「SEMPO」という作品そのものにも、強い感銘を受けた) が、生の舞台でそれを再確認したいという思いは、それからもずっと、私の中でくすぶりつづけていた。
今年、2013年の再演が発表されたときも、東京まで足を運ぶかどうか、まだ迷っていたのだが、折よく公演期間中の東京出張が決まったので、意を決してチケットを取ることにした――という次第である。
初めて訪れる新国立劇場・中劇場は、新宿からひと駅の初台駅直結とアクセスも良く、開場を待つためのスペースも、そして会場内のロビーもゆったりとしていて、とてもやすらげる空間だ。
ロビーには多くの花束が華やかに飾られていたが、残念ながら、中島みゆきからの花束はなかったようだ。
それはともかく、ロビーのバーで求めたシャンパンでひとり祝杯を挙げながら――暑い日だったので、シャンパンがことさら美味しい――開演前のひとときを過ごした。
全体的印象
上にも書いた通り、私はミュージカルというジャンルにはほとんどなじみがない。生の舞台でミュージカルを観るのは、実にこれが初めてのことである。
したがって、以下のレビューは、あくまでもひとりの中島みゆきファンの視点からの、ごくごく偏ったものになることをお許し願いたい。
――さて、同じ舞台作品である以上、これまでずっと観てきた中島みゆきの「夜会」との比較という点に、どうしても意識が向いてしまう。
その点でこのミュージカルからまず強く印象づけられるのは、なんといっても、構成や演出の「わかりやすさ」ということである。
「SEMPO」初演と同じ年に上演されたVOL.15「元祖・今晩屋」が、数ある夜会の中でもとりわけ「難解」な印象を与えた――私自身も、その第一印象を否定はしない――のとは、まさに好対照といってもよい。
たとえば、第一幕の中盤では、4人の女優さんがそれぞれ日本、イギリス、ドイツ、ロシアの役割を演じ、当時の国際情勢を歌で説明してくれるなど、歴史的知識が十分ではない観客にも、時代背景やストーリーが十分に理解できるように親切に構成されている。
大道具はほとんど机と椅子、階段ぐらいのシンプルなもので、回り舞台によるスムーズな場面転換によって、それぞれの場面が次々とわかりやすく呈示される。さらに舞台の外枠にはその場所(都市名など)も表示され、舞台の上には、外国人の観客向けに、英語字幕も表示される。
舞台背景全面に描かれた第二次大戦当時のヨーロッパの地図 (ストーリーの中心となるいくつかの都市がイルミネーションされている) や、休憩時や終演後の緞帳の、杉原千畝が書いたビザ実物の写真なども、物語の可視性を高めてくれる。
――こうした、さまざまな面での「わかりやすさ」は、「夜会」を見慣れた私にとっては、ある意味、新鮮でさえあった。
ただ、このように書いたからと言って、この作品は平板なエンターテインメントでは決してない。それは、この物語の主題の「重さ」からいって当然のことではあるのだが、それ以上に、主演の吉川晃司の存在が全体をしっかりと引き締めている点が大きい。
彼の歌唱と演技――というよりも舞台上の存在感そのもの――は、ミュージカルというジャンルに対して私が (これまでやや偏見まじりに) 抱いていたイメージとはむしろ逆に、とても内面的で真摯だ。
その内面性が、彼が歌う中島みゆき作品にふさわしいのは当然なのだが、何よりも杉原千畝という人物像のもつ歴史的リアリティをしっかりと支えている。
彼については、私は大昔のアイドル時代のおぼろげな記憶しなかったのだが、外交官というよりも一人の人間として、「国家」との板ばさみに苦悩しつつ、最後にはユダヤ人難民を救うためにビザを発給する決断に至るまでの千畝の心の揺れを、見事に演じきっていることに深い感銘を受けた。
――また、だからといって、全編が重くシリアスな雰囲気に塗りつぶされるというわけでも決してない。
シリアスなテーマに、良い意味でのエンターテインメント性を加味してバランスを取っているのは――この再演で新たに参加したAKB48のメンバーを含む女優陣、子役たち、そして何よりもユダヤ人難民を演じる大勢の人びとの――助演陣の熱演である。
彼女たちや彼らのおかげで、中島みゆきの「夜会」では――少数の例外的場面を除いて――まず観ることのできない、迫力ある群像劇としてのミュージカルの魅力を、十二分に堪能することができた。
「夜の色」
――さて、当然のことながら、中島みゆきが提供した6曲のことを抜きにして、このミュージカルを語ることはできない。
ファンの欲目をあえて承知の上で言えば、これらの6曲こそが、テーマの重さにふさわしい圧倒的な世界観の深みを「SEMPO」という作品に与えているのは明らかだろう。
第1幕最初の中島みゆき曲は「夜の色」。千畝のリトアニアへの転任の直前、前任地フィンランドの白夜の空を見上げながら、妻・幸子 (鈴木ほのか) とその妹・節子 (片山陽加) がデュエットで歌う。
白夜の色に人は騙され
見晴らすつもりで 夜を見ない
ここで白夜という自然現象に託して歌われるのは、人々が歴史の流れを――その向こうにあるかもしれない「闇」を――見通すことの困難さの暗喩である。
この曲によって一気に、舞台上の世界は立体的な奥行きを獲得する。客席の私は、単なる傍観者の視点を離れ、舞台上に構築される時空の中に連れ去られ、その参加者となる――
「愛が私に命ずること」
この曲は第一幕後半、ナチスドイツが侵攻したポーランドから脱出しようとするユダヤ人の青年ノエル (坂元健児) と、彼にともに脱出しようと誘われながらも、家族とともにその地にとどまる恋人エバ (白羽ゆり) とのデュエットで歌われる。
それは――かれらの以後の運命を予感させつつ――人びとが見通し難い歴史の流れに立ち向かう術 (すべ) を決然と呈示する歌でもある。
もしも愛と違うものが命ずることなら
従いはしない
心には翼がある
この歌を聴くと、私はどうしても、中島みゆきの1992年のアルバム『EAST ASIA』のタイトル曲を思い出してしまう。
山より高い壁が築きあげられても
柔らかな風は笑って越えてゆく
力だけで 心まで縛れはしない
抗いがたき歴史の激流と、それでもそれに抗おうとする心の自由――
このテーマの普遍性への思いこそは、このミュージカルへの楽曲提供へと、中島みゆきの背中を押したものだったのかもしれない。
「掌」「こどもの宝」
第2幕の中盤で千畝 (吉川) が歌うこの2曲は対をなしている。ここで彼は人生の岐路に立ちつつ、自らの「来し方、行く末」に思いをめぐらす。
何んでも出来ると 未来を誇っていたのは
小さな掌の少年の頃だけだった
自らの「やつれた掌」の無力さへの無念――そして、少年の頃の願い、夢、「宝」を忘れてしまっている自らへの幻滅。
今の私の願う宝は
あの子と同じものだろうか
――しかし、この過去への立ち戻りこそは、未来への新たな道を見出すためのステップでもあった。
第2幕の終盤近く、ずっと千畝と対立していたドイツ人秘書グッシェ (栗原英雄) が、ついにユダヤ人たちのビザ発給への協力に転じるとき、「こどもの宝」を歌いはじめる。この場面は、ある意味では千畝が歌う時以上に、この歌の意味を表現しきっていて強く胸を撃つ。
人生の岐路にあって、「こどもの宝」――すなわち「未来への夢」――を思い出す、ということの意味を。
「翼をあげて」
アルバム「DRAMA!」の冒頭を印象的に飾ったこの曲は、まず第二幕後半、千畝が妻・幸子に励まされ、ユダヤ人難民へのビザ発給を決断した直後に、二人のデュエットで歌われる。
ついで、さらに終盤、リトアニアの都市カウナスの駅の場面、ロシア (シベリア) を経て、遥か東方の地へと脱出しようとする列車の前で、ユダヤ人難民たちによる合唱。
それは、杉原夫妻にも、かれらによって救われることになる難民たちにも、ともに未来へと進むべき道を指し示す歌である。
恐れは消えはしない 生きる限り消えない
迷え 選べ 己れが最も畏れるものを選べ
――「恐れ」と「畏れ」との違いに注意したい。
かれらが「最も畏れるもの」とは何なのか。それはおそらくは、「口を塞ぐ者」「夢を捩る者」の力によっても屈することのない、縛られることのない、それがもたらす「恐れ」よりもさらに高いところにある何ものかである。
私はこのようなフレーズに、中島みゆきの「宗教性」――そう呼ぶしかないもの――の存在を強く感じる。それは、人間の有限性の認識と、人間を遥かに超えたもの――世界あるいは宇宙――への畏敬の念であり、次の「NOW」にも、あるいは夜会「今晩屋」の終曲「天鏡」にも、またさらにいくつかの中島みゆき作品にも、共通して存在するものである。
翼をあげて 今ゆくべき空へ向かえ
翼をあげて 向かい風の中
高く
――高らかな昂揚感、浮揚感、そして遥かなる希望への飛翔。このフレーズの響きと意味とをかみしめながら、私は大団円へと向かう流れに身を委ねた。
「NOW」
「SEMPO」の物語の時間、そこに登場するすべての人びとの思いは、終曲「NOW」へと奔流のように流れ込む。
舞台奥から客席に向けられた眩いバックライトの中を、まず千畝 (吉川) がひとりで歩み出しつつ、ソロで――見事な声量で――冒頭部を歌う。
やがて彼の家族や同僚が、ユダヤ人難民たちが、そしてこのミュージカルの出演者全員が次々と登場し、足並みを揃え、手を携えて前へと――光の方向へと――歩みながら、全員の大合唱となる。
今 ここは過去も未来もない
煩いを捨て 企みを捨て
我等は何を見つめるだろう
今 ここは過去と未来つなぐ
Right NOW
Right NOW
――過去と未来とをつなぐ “Right NOW”。
それは、夜会「24時着0時発」のタイトルそのものに表現され、冒頭の「サヨナラ・コンニチハ」や終盤の「無限軌道」で歌われる時間認識でもあった。
「SEMPO」の初演では、この曲はまず第1幕の冒頭で、ユダヤ人たちのリーダーの一人カイム (沢木順) によって歌われ、またカーテンコールでの出演者全員の大合唱でも歌われた。
だがこの再演では――熱狂的なスタンディングオベーションによるカーテンコールが何度も繰り返されたにもかかわらず――「NOW」は第2幕終結のただ1度だけしか歌われなかった。
しかし、それゆえにこそ、”Right NOW”という生涯でただ一度きりの時間のもつ意味を、私は、全身が震えるほどの圧倒的な衝撃とともに、体感することができたのだと思う。
エピローグ
「SEMPO」の2008年の初演と2013年の再演とのあいだには、あの2011年の大震災があった。
さまざまな重要なテーマを――「絆」といった、あれ以降一種の流行語になってしまった言葉とともに――いたずらに東日本大震災と結びつけて語ろうとする潮流には、私は与したくない。
――しかし、この「SEMPO」再演の舞台を観ながら、私は改めて――以前にこのブログの記事にも書いたことだが――あの災厄の直後、ワシントンD.C.のホロコースト博物館を訪れたときの記憶を思い返さざるをえなかった。
苦難の中にある人びとへの共感――といった月並みな表現では、その記憶の意味はとても語りつくせない。
苦難の中にあるのは、過去や遠い場所にいる見知らぬ人びとばかりではなく、まさに「今、ここ」にいる、この私自身でもあるのではないか――
主演の吉川晃司が、東日本大震災の被災者たちを「SEMPO」に招待したというエピソードも、そのような思いこそがもたらしたものだったのではないか――
そこにあるのは、自らを含む人間の有限性 (弱さや愚かさや哀しみ) を徹底して見据えつつも、それを諦念やシニシズムではなく、むしろ人間への限りない希望につなげようとする意志である。
その意志こそが、時間の流れを超えて、杉原千畝を、中島みゆきを、「SEMPO」に関わったすべての人びとを、そして客席にいた私たちを、遥かにつないでいるのだ。