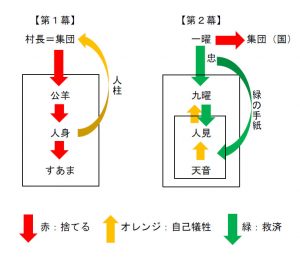1年以上も開店休業状態が続いたこのブログだが、さすがにこの記事だけは、いま書いておかなければなるまい (41枚目のニューアルバム『組曲 (Suite)』のレビューをはじめとして、他にもいろいろ書くべきことはあるのだが……) 。
1年以上も開店休業状態が続いたこのブログだが、さすがにこの記事だけは、いま書いておかなければなるまい (41枚目のニューアルバム『組曲 (Suite)』のレビューをはじめとして、他にもいろいろ書くべきことはあるのだが……) 。
12月17日(木)、大阪オリックス劇場でのコンサート「一会」に行ってきた。思い出してみるとこの日はちょうど、昨年の夜会『橋の下のアルカディア』の千秋楽から、1年と1日後にあたる。もうあれから1年が過ぎたのかと思うと、様々な意味でとても感慨深い。
諸般の事情で、この公演が私にとっての「初日」となる。ここ数年は、夜会でもコンサートでも、なるべく「ネタバレ」なしのまっさらの状態で臨みたいために、無理をしてでも (本当の) 初日の公演に出かけるようにしていたのだが、今回ばかりは散文的な事情のためどうしようもなかった。その代わりにというべきか、(ずっと以前にもそうしたように) ネット上各所で「ネタバレ」情報を仕入れ、十分に「予習」したうえで臨むことにした。
が、実際に接するライブでは、想像を遥かに超える中島みゆきとミュージシャンたちの「たぎり」に満ちたエネルギーの放射に、冒頭から圧倒され尽くすばかりだった。年内最終公演ということもあってか、ヴォーカルもバンドも思いの丈のすべてをほとばしらせるかのような激しい全力疾走で、私たちオーディエンスを巻き込みながら、一気にラストまで走りきったという印象だった。今もその心地よい余韻の中に浸りながら、この記事を書いている。
今回もまた、数々の魅惑的なイラストによって舞台の記憶を見事に再現してくれる、ぴしわさんの『覚え描き』ブログを参照させていただきながら、いま心に掛かっていることを書き留めていきたい。
サブタイトルの意味するもの
第1部、第2部それぞれの ~Sweet~, ~Bitter~ というサブタイトルは、第2部冒頭のお便りコーナーでかかるANN (オールナイト・ニッポン) のテーマ曲 “BitterSweet Samba” にちなんでもいるのだろうが、それと同時に、(過去の)「甘い」夢への追憶と、(現在から未来への)「苦い」現実の認識という意味をも、含んでいるような気がした。
第1部の舞台背景、廃墟と化した(?)海辺の遊園地の影絵は、冒頭の「もう桟橋に灯りは点らない」の歌詞とも相まって、喪われた過去の夢の象徴のようでもあり、「ピアニシモ」「ライカM4」では、中島みゆき自身の過去への思いをも織り交ぜながら、ラストの「MEGAMI」の「夢とも知らぬ夢」をみせる夜への誘いへとつながってゆく。
ここで話がいったん横道にそれるが、「ライカM4」の前、デビュー当時の自身の「写真嫌い」のことを語る中島みゆきのMCを聴いて、、ずっと以前に書いた記事のことを思い出した。その記事で私は、ファーストアルバム『私の声が聞こえますか』のモノクロームのジャケット写真、高い空の下に広がる白い雪原をうつむき加減に歩いてくる中島みゆきの姿を、中島みゆきと――私たちオーディエンスを含む――世界との関係の視覚的表象の記憶として言及した。
あのファーストアルバムの制作には、アレンジ等も含め多くの点で、中島みゆき自身の意志が必ずしも反映されていないことは、熱心なファンにはよく知られている事実だろう。ジャケット写真もその例外でないことは、今回のMCで、よりはっきりしたと言ってもいい。だが、むしろそうであればこそ、あのジャケット写真は――いわば、自らが踏み込もうとする世界への中島みゆき自身の「違和」の視覚的表象として――現在も意味を持ちつづけているように思う。
――とはいえ、そのような違和を脱して、自らの姿を風景の中に透明に写し出してくれる写真家、タムジンこと田村仁氏に出会えたこと、そして彼がいまも、彼女の視覚的表象を私たちに届け続けてくれていることが、中島みゆき自身にとっても私たちにとっても、幸福な出会いであったことは、改めて強調するまでもないことだ。
第2部冒頭のANNの再現は、懐かしくかつコミカルではあるが、その「深夜」のイメージが一転して「ベッドルーム」の「闇」へと移る衝撃は、まるでANNの「最後の葉書」での徹底的にシリアスな語りへの転換のようでもある。
そして、それ以降の強烈なメッセージに満ちた曲の連続は、やはり通常のコンサートツアーとは明らかに異質な何か――中島みゆきが「一会」と名付けたこのコンサートにこめた思いの強さと深さ――を強く感じさせた。
それらの「苦さ」に満ちたメッセージの中でも、おそらく最も核心に位置しているのが「阿壇の木の下で」。凄まじい爆音のSEの中から、それをなお突き抜けて、眩くほとばしる輝きのように、優しく力強くどこまでも伸びてゆく声――
この曲の内容の解釈めいたことは、ここでは控えたい。ただ、この曲で中島みゆきが初めて手にする赤い紐――両手の間に架け渡そうとしては、繰り返し片手を離し、片方を垂れ下がらせるというパフォーマンス――は、まるで、人と人、地域と地域、あるいは国と国とのあいだに「届かない」思い――それが「届かない」ことのもどかしさ、口惜しさ、そして憤ろしさ――の象徴のようにも見えた。
それ以降、「Why&No」まで中島みゆきがその赤い紐を首にかけつづけるのは、それらの「届かない」思いを、自らへの問いとして引き受け続ける覚悟の表明でもあったのだろうか。
深夜に始まった第2部は、ラストの「麦の唄」での朝の光の訪れで幕を閉じる。この曲の最大の聴きどころ、遥かな時空を超えてゆくかのように転調を繰り返す3番――
どんなときも届いてくる 未来の故郷から
「故郷から」の最後の音を伸ばし、5小節も続くロングトーン――そしてそれを歌いきる中島みゆきの素晴らしい輝きに満ちた表情。それは、すべての現実の「苦さ」を超えてなお、ゆくべき未来に辿り着こうとする強靭な意志と希望との表現でもあるように見えた。
第3部 ~Sincerely Yours~ と題されたアンコールは、その名のとおり、私たちオーディエンスへの結びの言葉。
ラストの優しい軽みに満ちた「ジョークにしないか」には予想以上に意表を衝かれたが、本編とりわけ第2部のメッセージがあまりにも苦い重みに満ちていたからこそ、語りきれない、伝えきれない「きりのない願い」は、それを正面から語る代わりに「ジョークにしてしまおう」といなすことで、私たちの肩の荷を軽くしてくれたような気もした。
音楽的印象
ミュージシャンたちの中で、とりわけ個人的に印象に残ったのは、杉本和世・宮下文一・石田匠のコーラス3人と、ストリングスのトップの牛山玲名。
「超音波和ちゃん」の面目躍如ともいうべき「やまねこ」、繊細な輝きに満ちた「MEGAMI」のハーモニーでの杉本和世の美しい高音。そして「Why&No」で中島みゆきがいったん退場した後を引き継ぎ、3人が次々に歌うところでの、それぞれの個性と表情に満ちた力強い歌声。
牛山玲名のバイオリンは「ピアニシモ」などでのソロの繊細な演奏も印象的だったが、「一会ストリングス」の7人を見事にリードし、オーケストラでいうところのコンサートマスター役を果たしていたように感じた。
トリプル・キーボードとツイン・ギター、久しぶりに参加するパーカッション、そして上述の7人のストリングスを加えたバンドの音の厚みは、通常のライブでの編成をはるかに上回る。にもかかわらず、一糸乱れぬ緊密・繊細かつパワフルなアンサンブルが、島村英二・富倉康生の盤石のリズムセクションに支えられながら、中島みゆきの力強いヴォーカルに鋭敏に呼応し、揺るぎなくサポートしつづけるのは、見事というほかはない。
余韻
終演後は、約四半世紀ぶりの参加メンバーも含め、古くからのみゆきファン仲間である「歌暦ネット」の懐かしい面々と再会。杯を傾け、パソコン通信時代の懐かしい話に花を咲かせつつ、痺れるようなライブの余韻に浸ることができた。かつて、ともに中島みゆきを追いかけて旅をし、いまはもう「会えない相手」となった何人かの仲間たちもまた、コンサートの時からずっと私たちと一緒にいて、笑っていてくれたような気もした。
「阿壇の木の下で」の前のMCで中島みゆきが語っていたように、数十年も前から「何も変わっていない」もの――現実の「苦さ」や「届かない」思い――が、私たちの暮らすこの国にはいまも確かにある。志半ばで「会えない相手」となった彼ら、彼女たちにとっても、おそらくは心残りだったであろう、それらの「届かない」思いの数々を――中島みゆきとともに――自らへの問いとして受け継いでゆくことが、この国の現在を、そして未来を生きてゆく私たちが引き受けるべき課題でもあり、そして希望でもあるような気が、私にはした。
セットリスト
- 「もう桟橋に灯りは点らない」
- 「やまねこ」
- 「ピアニシモ」
- 「六花」
- 「樹高千丈 落葉帰根」
- 「旅人のうた」
- 「あなた恋していないでしょ」
- 「ライカM4」
- 「MEGAMI」
- 「ベッドルーム」
- 「空がある限り」
- 「友情」
- 「阿檀の木の下で」
- 「命の別名」
- 「Why & No」
- 「流星」
- 「麦の唄」
- 「浅い眠り」
- 「夜行」
- 「ジョークにしないか」
- 小林信吾 (Conductor, Keyboards)
- 中村 哲 (Keyboards, Saxophone)
- 飯塚啓介 (Keyboards, Manipulation)
- 古川 望 (Guitars)
- 福原将宜 (Guitars)
- 富倉安生 (Bass)
- 島村英二 (Drums)
- 三沢泉 (Percussion)
- 杉本和世 (Vocal)
- 宮下文一 (Vocal)
- 石田匠 (Vocal, Guitar)
- 牛山玲名 (Violin)
- 田島華乃 (Violin)
- 中島優紀 (Violin)
- 民谷香子 (Violin)
越川歩 (Violin) - 友納真緒 (Cello)
- 関口将史 (Cello)